高尾事務所は、愛知県社会保険労務士会、愛知県行政書士会に所属しています。
労働者派遣事業許可申請CONCEPT
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
一般労働者派遣事業…
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業…
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。
※一般労働者派遣事業の許可を受け又は受けようとする事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請が必要です。
「常時雇用される労働者」とは
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には
① 期間の定めなく雇用されている労働者
② 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者
(1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
③ 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
(1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。
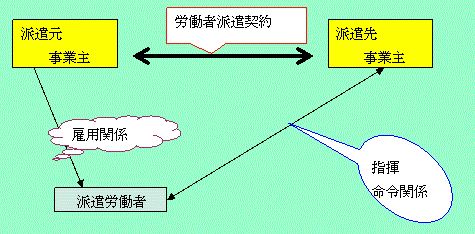
一般労働者派遣事業 提出書類
| 法人の場合 | 個人の場合 |
|---|---|
| 定款又は寄附行為 登記簿謄本 役員の住民票の写し及び履歴書 貸借対照表及び損益計算書 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し 法人税の納税証明書(その2所得金額) 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 派遣元責任者が「派遣元責任者講習」を受 講したことを証する書類の写し 個人情報適正管理規程 |
住民票の写し及び履歴書 所得税の納税申告書の写し 所得税の納税証明書(その2所得金額) 頭金残高証明書 不動産登記簿謄本の写し 固定資産税評価額証明書(資産) 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 派遣元責任者が「派遣元責任者講習」を受 講したことを証する書類の写し 個人情報適正管理規程 |
法人の資産要件
資産合計額-(繰延資産・営業権合計額)-負債の合計額=基準資産額
要件1
基準資産額≧2,000万円×事業所数( )
要件2
基準資産額≧負債の総額×1/7
要件3
現金・預金の額≧1,500万円×事業所数( )
※ポイント
有効期間3年更新が必要
許可申請書に12万円の収入印紙貼付
派遣元責任者講習の受講
派遣元責任者は、職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
(社団法人日本人材派遣協会(新規ウィンドウが開きます))にお問合せ下さい。
特定労働者般派遣事業 提出書類
| 法人の場合 | 個人の場合 |
|---|---|
定款又は寄附行為 登記事項証明書(登記簿謄本) 役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。)の写し及び履歴書 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動書 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規程 |
住民票(本籍地の記載のあるもの。)の写し及び履歴書 所得税の納税申告書の写し 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規程 |
※ポイント
常用労働者のみの派遣であれば、特定で十分
有料職業紹介事業との関係
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋することをいいます(下図参照)。
この場合、あっ旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。
手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができます。